2010年10 月11日 (月)
2010年9 月30日 (木)
横浜市 耐震改修工事の補助金2
よくある質問シリーズ第2弾
Q3、建築確認通知書をなくしたけど無料診断できるの?
A3、新築が昭和56年5月以前の着工であれば、横浜市の無料診断は受けられます。実際に補助金の申請業務を進める時、お手元にない場合は市役所で過去の資料を調べることができます。こういった資料は工務店や設計事務所が代理で調べてくれる場合が多いですので、確認通知書がない旨をご相談ください。
Q4、新築は昭和56年5月以前だけど、その後増築しているので補助金申請は無理ですか?
A4、新築時が昭和56年5月以前であれば、その後増築していても対象にはなります。ただし、増築部分の面積が新築時の延べ床面積の2分の1以内であることが条件です。また増築した箇所の形状が、現在の建築基準法に適合していなければ補助金がおりませんので注意が必要です(増築した箇所だけでなく、新築時の形状も基準法に適合していなければなりません)。万が一面積や形状が現況で適合していない場合でも、耐震改修工事完了時までに修繕するという申請を行えば、補助金の対象となります。
Q5、耐震改修工事と一緒に少しだけリフォームをしたい。リフォームにも補助金を充てられるの?
A5、横浜市の制度では耐震改修工事に対してのみ補助金がおります。リフォーム工事に対しては補助金はおりません。ただし耐震改修工事のために剥がした壁の下地やクロスは、工事箇所のみ補助の対象になります。職人会で補助金を利用して耐震改修工事を行われる方のほとんどは、耐震改修工事を機にリフォームを行っています。同じ機会にリフォームした方が時間的にも予算的にも無駄がないため、こちらからもオススメしています。
よくある質問シリーズ つづく。
よくある質問シリーズ第1弾は こちらのページ です。
ご質問がありましたらコメント、もしくはメール [email protected]へ ご連絡ください。
記事として取り上げさせていただく場合もございます。
2010年9 月24日 (金)
木耐協 無料耐震診断
日本木造住宅耐震補強事業者共同組合 略して「木耐協」
耐震補強工事を行う業者が加入する全国組織です。
HP http://www.mokutaikyo.com/ 職人会は木耐協の組合員です。
9月1日にNHKで、木耐協が実施する無料耐震診断についての報道があり、
全国から問い合わせが殺到しているようです。
木耐協では問い合わせを受けた場合に、担当エリアの組合員を通じて診断を行います。
職人会も先週から木耐協としての無料耐震診断を行うため、忙しく動いています。
無料耐震診断をするのは、木耐協が定める「一般耐震技術認定者」で、
各自認定者証を持っています。こちらをお客様へ提示するのが義務になっています。
こういうグリーンのカード。診断を受ける方は必ず確認してください。
耐震補強(改修)工事、まずは診断から。
木耐協の無料耐震診断の条件は以下の3つ、全てを満たしていることです。
・木造在来工法2階建て以下の家屋であること
枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。
・持ち家であること
借家の物件の耐震診断は承ることができません。
・昭和25年以降平成12年5月までに着工された家屋であること
平成12年6月に建築基準法が現在のもにに改正され、耐震に関する基準が強化されました。その後に建築された家屋は基本的に改正後の建築基準法に則って建てられているため、耐震診断は承っておりません。
無料耐震診断お申込はこちらです![]()
木耐協 受付専用フリーダイヤル 0120-249-761
または木耐協ホームページから http://www.mokutaikyo.com/nagare/index.htm
ちょっと気になること、聞いてみたいことがございましたら、職人会へどうぞ![]()
職人会 フリーダイヤル 0120-660-238
2010年9 月17日 (金)
ありがたい網戸
7月の事務所改装によりサッシを交換した職人会です。
この度初めて網戸が入りまして、その有難さに社員が喜んでいます![]()
というのも、網戸なしで窓を開けると、蚊がすぐに入ってきてしまう状態で、
ちょっと暑いとすぐにエアコンという具合でした。
数日前からやっと涼しい風が出てきて、窓を気持ちよく開けています。
やっぱり自然の風がイチバン![]()
網戸と言えば、家の網戸も悪くなってきたなぁ、と思っている方。
LLP職人倶楽部よこはまが主催するハウスメンテマスター検定で、
網戸張替え、襖張替えの実技講習を行います。開催は12月5日(日)。
これまで網戸張替えのご経験がある方でも、プロっぽく仕上がる!と好評です![]()
2010年9 月12日 (日)
アステックペイント 住まいの健康を守る
塗装したては気持ちよいくらいきれいですが、時間の経過と共に外壁のひび割れや汚れが気になってくるものです。塗装材料の役割は建物の美観を保つことはもちろん、より永く住み続けるために住まいの健康を守ることです。ひび割れから水が浸入すると建物の躯体が腐ったり、それが原因でシロアリの被害に遭ったり、湿度が高くなって室内にカビが生えたりという問題が発生します。また外部環境によって藻が生えやすかったりすると塗料の性能が落ちるだけでなく、見た目にも美観を損ねてしまいます。
アステックペイントは塗料の伸縮性が高いので、表面のひび割れを防ぎ、水の浸入をシャットアウト。紫外線に対する高い耐久性を持ち、塩害や酸性雨にも強い特徴を持ちます。またカビの発生を防ぐ機能もあり、長期間にわたりその効果を発揮するのです。
経済性は、一般の塗装材料と比較して30万円ほど割高ではありますが、耐久性が高いため次回塗替えまでのスパンが長いこと、また、2回目以降は下塗りが不要であるため、トータルのコストは抑えることができます。ですので、築年数が浅く今後2回以上の塗替えの予定があるお宅や、新築住宅にオススメです。
水性塗料であるため工事期間がかかってしまうというデメリットがありますが、塗料自体の臭いが気にならずご近所の方へ迷惑をかけることはありません。また人体への健康被害が懸念される揮発性有機化合物(VOC)の発生も1%以下ですので影響はありません。
アステックペイントは、株式会社アステックペイントジャパンの製品です。メーカーホームページはこちらhttp://www.astec-japan.co.jp/
詳しい資料・ご相談をご希望の方は、職人会へお電話くださいね!
2010年9 月10日 (金)
横浜市 耐震改修工事の補助金 @港南公会堂
職人会が所属する組合「LLP職人倶楽部よこはま」主催 横浜市 耐震補助金の利用説明会を港南公会堂にて開催しました。港南公会堂での開催は5回以上を数え、現在港南区では耐震改修工事の進んでいる現場が数棟あります。弊社代表の小林が講師を務めています。本日は7名の方が来場されました。
各区公会堂での説明会の開催は午後2時から4時の2時間で、前半は木造住宅の構造と地震の話、後半は補助金を受けるための条件と申請の流れについてのお話をさせて頂きます。非常にややこしく、難解な「耐震」ですが、より分かりやすい説明会を目指して毎回改良を重ねています。2時間ではとても時間が足りないくらいですが、ぎゅっと凝縮し、大切なポイントをご理解頂けるよう心がけています。
次回は
9月17日(金)瀬谷公会堂
9月28日(土)泉公会堂 です。ご予約の上ご参加くださいね! 0120-660-238
よくある質問を解説します。
Q1、耐震工事って高くつくんでしょう?
A1、横浜市の補助金を利用するには評点1.0以上を目指す必要があり(利用の条件であるため)、お宅によって工事内容が異なるため工事費用には幅があります。また、耐震改修工事を機にリフォーム工事を行うお宅もあり費用には差が出ます。これまで弊社が行った耐震改修を含む工事の費用は、最低180万円、最高800万円です。なお横浜市の資料によると、設計・工事を合わせた耐震改修合計の費用の平均は340万円、主な分布は150から600万円とのことです。(横浜市建築局発行「耐震改修のすすめ」より)
Q2、横浜市の補助金の上限150万円ちょうどで工事を済ませたいのだけど・・・
A2、横浜市の補助金利用は改修工事後の評点が1.0以上となることが条件です。評点は工事前にパソコンのソフトで計算し、その計算した設計通りに工事を行うことで工事後の評点が決まります。設計の時点で1.0未満ですと、工事が終わっても補助金を利用することができません。あくまで評点をが1.0以上となる工事に対し上限で150万円が補助される制度ですので、ここからは個別での相談が必要となります。
よくある質問シリーズ 続く
2010年7 月20日 (火)
蟻害から住まいを守る
前回はシロアリの特徴をお伝えしました。その続きです。
今回この記事は、シロアリ業者のアイジーコンサルティング、重田さんの監修でお送りします![]()
蟻害から住まいを守るためには、
①防蟻する(薬剤処理)
②プロの目で定期的に点検してもらう
③シロアリを呼ぶ原因をつくらない
この3点が重要ポイントです。
まず、シロアリの形跡とはどのようなものなのか見て行きましょう。
床下ではなく普段私達の目から見える場所で確認できるシロアリの形跡です。
一つ目は浴室や洗面所の出入り口。建具などの木枠の根元部分です。
腐って穴があいていると既に被害に遭っています。
二つ目はお庭。木製の柵や植え込みの支柱の根元部分です。
土のかたまりが付いていたら、確実にシロアリがいます。
お庭の場合は、イコール建物の被害ではありませんが、
自分の家の周りにシロアリがいるということを意味します。
三つ目は建物の中。羽蟻が大量にいた場合です。
シロアリは特に5月~6月にかけて飛びます。
夏の今の時期はクロアリの羽蟻が飛ぶ時期です。
しかし夏の羽蟻がクロアリだからと言って安心はできません。
クロアリが大量に飛んでいる場合は、
建物に何か異常があることを疑わなくてはならないからです。
その理由は、
①クロアリがシロアリを食べに来ている
②水漏れ、結露にクロアリが集まっている
ということが考えられるのです。
特に水漏れは建物の大敵ですね。浴室周りや台所は注意しましょう。
また重田さんの経験上、出窓部分の水漏れ・雨漏れが多いとのことです。
兆候が現れているときには、もう既に被害に遭っていると考えなくてはなりません。
木造住宅の大切な構造体の土台や柱を食べてから、目に見えるところに現れるからです。
先の ①防蟻する が重要なのは、このためです。
新築住宅も既に建っている住宅も、条件さえ整えば、いつでもシロアリに食べられてしまいます。
建物の築年数に関わらず、薬剤の効き目が続いている建物は安心です。
兆候や形跡が目に見える前に対策することが、シロアリから住まいを守る最善の方法です。
薬剤の効き目(薬効)はおよそ5年間。
その間、1度薬効の確認をします。防蟻処理から2年半後です。
それが ②プロの目で定期的に点検してもらう ことです。
シロアリ業者に依頼すると床下にもぐったり、家の周りをくまなく見てくれたりします。
実際シロアリの姿を確認するのはもちろん、その兆候や形跡を調査してくれます。
しっかりと薬効が認められれば、安心して次回の防蟻処理の時期を待つことができますね。
床下点検の流れについてはこちらをご覧下さい。
そして最後に ③シロアリを呼ぶ原因をつくらない こと。
私たち、住まい手ができる対策も覚えておくと良いでしょう。
床下換気口を塞がない
鉢植えや物置が基礎の換気口を塞いでいませんか?
地面に直に木材を置かない
シロアリの格好のエサですよ。
水漏れ雨漏れを放置しない
構造体が腐り、床下に湿気がたまり、シロアリが集まります。
この機会にぜひ家の内外を見回し、住まいの安全・安心について考えてみてくださいね。
重田さんからのこぼれ話ですが、
景気が悪くなってからの方が、シロアリ業者の出番が多いそうです。
建て替えを控える代わりに、今ある家を長持ちさせることを考える方が増えたようですね。
大切なわが家を守りましょう。職人会がお手伝いします。
![]() アイジーコンサルティング 重田さん、ありがとうございました!
アイジーコンサルティング 重田さん、ありがとうございました!![]()
2010年7 月14日 (水)
シロアリの特徴
シロアリによって建物が受ける被害を「蟻害(ギガイ)」といいます。
こちらはシロアリの写真です。
写真左から、羽蟻、職蟻、兵蟻です。すべて同じヤマトシロアリです。
普通の蟻(クロアリ)との違いはまず形。
シロアリは寸胴なのに対して、クロアリはくびれがしっかりあります。
また表皮は、シロアリは柔らかいのに対し、クロアリは硬い皮膚で覆われています。
よーく見ると、羽にも違いがあります。
シロアリは4枚同じ長さなのに対して、クロアリは前の羽が大きい形です。
色はシロアリもクロアリも土色です。
シロアリ被害の中には木造住宅の構造自体に影響を及ぼすケースもあります。
なぜシロアリは家を食べるのでしょうか?
シロアリは昔から森の木を土に還すという循環の中で生きてきました。
人間が作った家の柱や土台も、シロアリにとっては森の中の木と変わりません。
木の比較的柔らかい部分から食べては、土に還すという営みが木造住宅で起きているのです。
シロアリは暗くて風通しが悪く、湿気の多い場所を好みます。
光や通風、乾燥が苦手で、実は非常に弱い生き物なのです。
条件が整わなくては生きることができません。
ところが木造住宅の床下や浴室回りは、シロアリの好む条件が整いやすい環境です。
そのため、戸建住宅の多くが木造である日本で、シロアリ被害が絶えない現状があります。
どうしたら蟻害から住まいを守ることができるのか・・・
続きは次回。


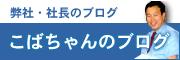
最近のコメント